国民年金の給付について
お問い合わせ先:福祉・こども課 福祉・児童家庭係 電話(0980)56-2198

国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金と、寡婦年金、死亡一時金、付加年金の3つの独自給付により、あなたの生活を守ります。給付を受けるためには、一定の要件が必要となります。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間が原則として10年以上ある方(免除期間も含む)が65歳を基本として60歳から請求することができる年金です。60歳で繰上げ請求した場合の年金は減額され、65歳以上で繰下げ請求した場合は増額されます。
|
配偶者がいる場合
|
単身者の場合
|
|---|---|
|
|
障害基礎年金
国民年金加入中(初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上を納付または免除、または初診日の前々月までの1年間に未納がないこと)や20歳前などの病気やけがで障害が残り、年金上の障害等級1級または2級の状態になった場合に支給される年金です。
申請の際に必要なもの
それぞれの状況に応じて必要な書類が異なります。お近くの年金事務所か役場福祉・こども課へご相談ください。
遺族基礎年金
次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子(注釈)」が受け取ることができます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 平成29年7月までに老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき
(注釈)子
- 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること
(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。 - 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
- 婚姻していないこと
申請の際に必要なもの
- 年金手帳または年金証書(死亡者・請求者ともに)
- 死亡診断書
- 所得証明書(請求者)
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 住民票除票
- 印鑑
- 預金通帳
- 在学証明書(高校生の場合)
寡婦年金
国民年金第1号被保険者*(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
注意事項
- 以下に該当する方は請求できません。
- 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合。
- 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合。
- 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合。
- 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合はどちらか一方を選択して受け取ることとなります。
申請の際に必要なもの
- 死亡した夫の年金手帳
請求者が公的年金制度等から年金の支給を受けている場合はその年金調書(恩給証書)の写し - 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 印鑑
- 預金通帳
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料を3年以上納めた方が年金を受給せずに亡くなり、遺族基礎年金を受けられない遺族に対して支給されます。
死亡一時金については、保険料を納めていただいた期間に応じて額が決まります。
|
保険料納付済期間
|
一時金の額
|
|---|---|
|
3年以上15年未満
|
120,000円
|
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
付加保険料納付済期間が3年以上の場合は8,500円が加算されます。
注意事項
- 請求できるのは、死亡日から2年以内ですのでご注意ください。
- 全額免除の期間は計算されません。また寡婦年金とどちらかを選択することとなります。
申請の際に必要なもの
- 死亡した夫の年金手帳
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 住民票除票
- 印鑑
- 預金通帳
別居の方が請求する場合は「生計同一申立書」が必要となります。
付加年金
第1号被保険者や任意加入の方に限り、月額400円を納めると、老齢の基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の納付を希望される方は、年金事務所に申し出てください。
注意事項
- 国民年金基金に加入している方は、付加年金に加入できません。
- 保険料の免除承認期間については、付加年金を納めることはできません
未支給請求
年金は死亡した月の分まで支払われますが、遺族は年金受給者が死亡したことを役場年金係か年金事務所に届出(年金受給権者死亡届出)なければなりません。また、死亡した月に支払われるはずであった年金が残っていた場合、遺族の方(死亡当時年金受給者と生計を同じくしていた1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母または兄弟姉妹)が請求をすれば、その分の年金が支払われます。
注意事項
年金受給権者死亡届出が遅れると、多く受け取った分の年金を返納しなければならなくなりますのでご注意ください。
届出の際に必要なもの
- 死亡者の戸籍謄本
- 住民票除票
- 住民票抄本(請求者)
- 年金証書(死亡者)
- 印鑑
- 預金通帳(請求者)
このほかにも添付書類が必要な場合があります。
年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金(2019年10月から制度開始)
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
支給の対象となる方
【老齢基礎年金を受給している方】
(以下の要件をすべて満たしている必要があります)
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が88万円以上である
【障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方】
(以下の要件を満たしている必要があります)
・前年の所得税が約462万円以下である
2020年1月以降に請求した場合は、請求した月の翌月分からお支払いとなります。
速やかな請求手続きをお願いします。(遡ってのお支払いはできません)
特別障害給付金制度について
国民年金の任意加入対象者であった方が、加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給することができない障害者の方について、国民年金制度の福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
支給の対象となる方
現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方で、任意加入していなかった期間に初診日があり、平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(厚生年金保険、共済組合等加入者・老齢給付受給権者、受給資格期間満了者、議員等)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
申請の際に必要なもの
それぞれの状況に応じて必要な書類が異なります。お近くの年金事務所か役場福祉・こども課へご相談ください。
その他
年金の受給にあたっては、それぞれのケースに応じて請求要件がありますので、詳細については、お近くの年金事務所、共済年金関係は各共済組合等にお問い合わせください。
国民年金相談窓口
名護年金事務所
電話
0980-52-2522(代表)
ファックス番号
0980-52-6349
開庁日
月曜日~金曜日(国民の休日及び年末年始の休日を除く)
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分
ねんきんダイヤル
お問合せ先
電話
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)
受付時間
月曜日 午前8時30分~午後7時
火曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
- 月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
- 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉・こども課 福祉・児童家庭係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
FAX番号:0980-56-4270
電話番号:0980-56-2198

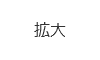









更新日:2023年10月10日